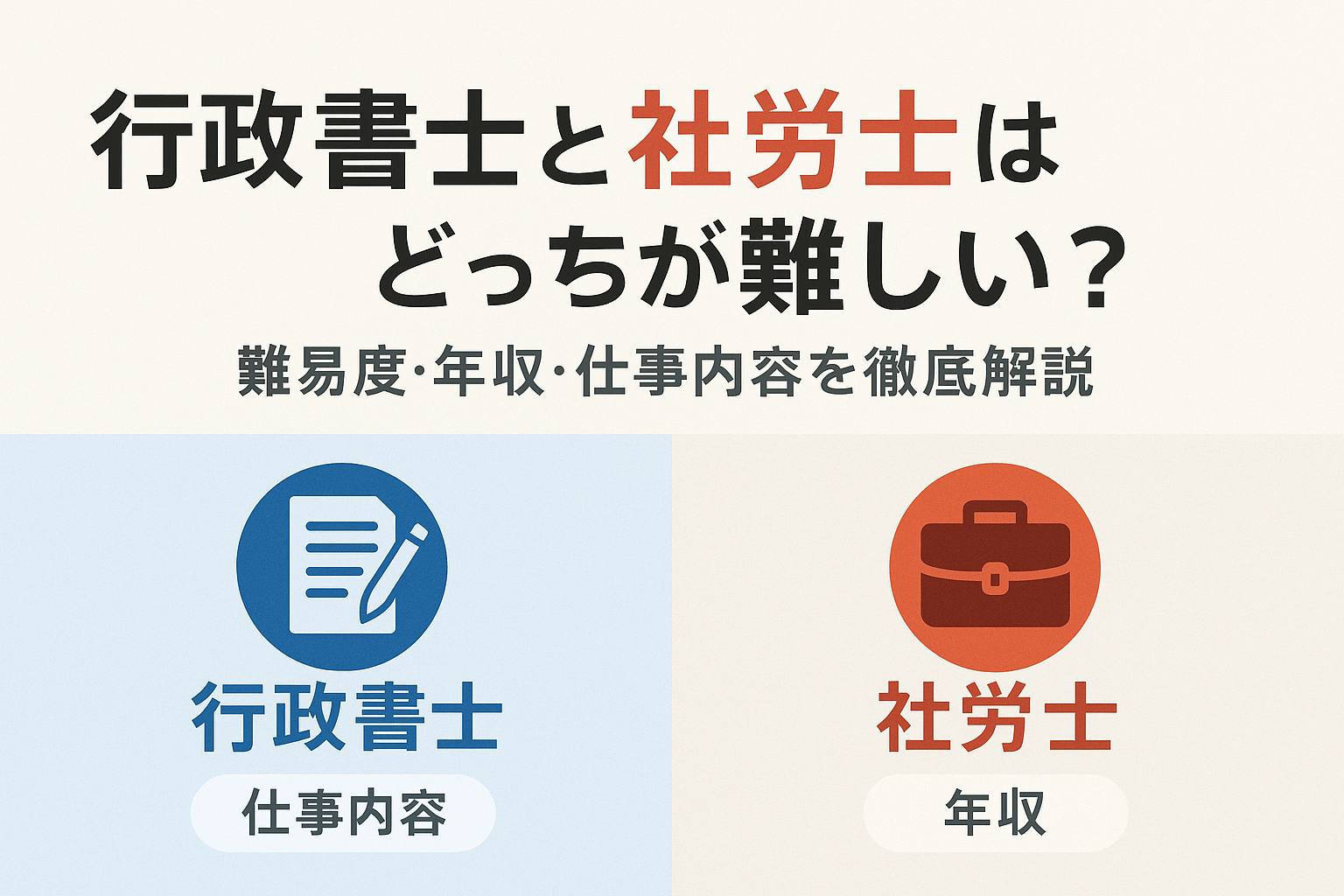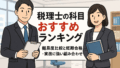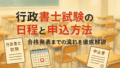行政書士と社労士、どちらの資格が自分に合っているか悩んでいませんか?「試験の難易度は?」「年収は本当に違うの?」「独立や転職で有利なのはどちら?」――資格選びの場面で必ず直面する疑問です。
一例として、行政書士試験は全国で毎年約4万人が受験し、合格率は【10%台】。主に官公庁への許認可申請や法律文書作成で活躍します。一方、社労士試験は受験者数が約5万人、合格率は【7%前後】。労働・社会保険手続の専門家として【企業からの安定した需要】があり、顧問契約による月額報酬モデルを築く方も多く見られます。
年収面でも違いは明確です。一般的に行政書士の平均年収は【400万円台】、一方で社労士は【500万円台】とやや高く、ダブルライセンスの場合は【600万円以上】を目指せるというデータも。もちろん、実務経験や独立開業の有無によっても大きく差が生じます。
「どちらが自分の将来設計に合っているのか?」この選択を誤ると、せっかくの努力も無駄になってしまいかねません。ですが安心してください。本記事は、行政書士と社労士それぞれの【業務・試験・年収・独立】という「実データ」と現場のリアルに基づき、迷いや疑問を一つひとつ丁寧に解消していきます。
「最後まで読むと、自分の適性やキャリアプランにベストな資格選びのヒント」が必ず見つかります。損しない判断のために、ぜひじっくりご覧ください。
行政書士と社労士はどっちが難しい?仕事・年収・キャリアの全体像を徹底比較
行政書士と社労士は、士業のなかでも高い人気を持つ国家資格です。どちらも独占業務を持ち、仕事や将来性、難易度や年収など多くの観点で比較されています。下記のテーブルで違いを整理します。
| 比較項目 | 行政書士 | 社労士 |
|---|---|---|
| 難易度 | 合格率10〜15%、記述式あり | 合格率4〜7%、選択・択一式 |
| 必要な資格要件 | 誰でも受験可 | 原則大卒以上など条件あり |
| 主な業務 | 許認可申請、契約書作成など | 社会保険手続、労務相談など |
| 年収目安 | 400万〜800万円(独立型は幅あり) | 500万〜900万円(安定傾向) |
| 独立のしやすさ | 比較的容易 | 顧問化できると安定 |
| 将来性 | AI・DX影響を受けやすい業務もある | 人事・労務分野の需要安定 |
このように、どちらも専門性と独自性が高く、今後も需要が見込まれています。どっちが難しいか、どっちが稼げるかは自分の適性や希望する働き方次第です。
行政書士の役割と具体的な業務内容 – 公的手続きを主に担う法律の専門家
行政書士は官公署への申請代理や法律関連の書類作成を幅広く担当します。依頼主のニーズを汲み取り、手続きを正確・迅速に進める手腕が求められます。主な業務は次の通りです。
-
許認可申請の代理(建設業、飲食業、法人設立など)
-
権利義務や事実証明に関する書類作成
-
官公署への提出書類の作成・相談対応
特に起業や新規事業に関連した申請サポートは需要が高く、多くの法人・個人事業主から頼られています。
許認可申請代行や権利義務書類作成など行政書士独占業務の詳細 – 具体的手続きや成果物例
行政書士独占業務は多岐にわたります。代表的なものは次の通りです。
-
建設業許可申請や宅建業免許申請の代理
-
農地転用、古物商許可など各種許認可手続き
-
遺産分割協議書など権利関係書類の作成
-
外国人在留資格取得支援
これらの手続きは、専門知識や実務経験が求められるため、プロの行政書士に依頼されるケースがほとんどです。
社労士の役割と具体的な業務内容 – 労務管理・社会保険の専門家としての業務範囲
社労士は企業の人事・労務分野で欠かせない存在です。従業員の入退社管理や社会保険への手続き、求職者支援など、職場の円滑な運営を側面からサポートします。主な業務は以下の通りです。
-
労働・社会保険手続きの代理提出
-
就業規則や賃金規程の作成・改定
-
労務相談(働き方改革、有給管理、労働トラブルの予防や対応)
日々の管理業務からトラブル対応まで幅広くカバーし、職場のコンプライアンス向上に貢献します。
労働保険・社会保険手続き代行、就業規則作成など社労士独占業務解説 – 支援できる業務範囲と現場事例
社労士の独占業務は、次のような分野で力を発揮します。
-
社会保険・雇用保険・労災保険の新規・変更・喪失届の提出
-
労働保険の年度更新や算定基礎届の申請
-
就業規則・各種諸規定の作成と見直し
-
労働トラブル・労使紛争の相談やアドバイス
特に労働基準法や社会保険法に直結する実務で説明責任が求められるため、専門資格でしか対応できない場面が多数あります。
行政書士と社労士の業務範囲の重複と相互補完性 – ダブルライセンスの強みを踏まえて
行政書士と社労士の資格を両方持つことで、より幅広いサービスを顧客へ提供できます。それぞれ単独では対応しきれないシーンも、両資格なら一貫性を保てるメリットがあります。
-
会社設立から許認可申請・社会保険手続きまでワンストップ化
-
顧客拡大・高単価案件につながる可能性
-
コンサル業務や複数の士業との連携による差別化
このように業務分野は一部重複しますが、行政手続き+労務管理という両面サポートができる点はダブルライセンスだけの大きな魅力です。
行政書士と社労士はどっちが難しい?試験難易度・合格率・勉強時間を徹底比較
試験科目・出題範囲の違いの詳細 – 法令科目と専門分野の焦点差
行政書士と社会保険労務士(社労士)の資格試験は、出題範囲と専門性に大きな違いがあります。
| 試験名 | 主な対象 | 主な科目 | 法令科目 | 専門分野 |
|---|---|---|---|---|
| 行政書士 | 行政手続・法律全般 | 憲法、民法、行政法、商法、一般知識 | 法令6割超 | 複数法分野横断型 |
| 社労士 | 労働・社会保険 | 労働基準法、雇用保険法、健康保険法、社会保険法等 | 法令&計算問題 | 労働保険・社会保険 |
行政書士は幅広い法律知識が求められ、社労士は労働・社会保険分野の深い専門知識と計算力が重視されます。
行政書士試験の特徴的な記述式問題と一般知識のポイント – 合格のための重要領域
行政書士試験の特徴は、択一式に加えて、実際の法律運用能力を問う「記述式問題」がある点です。法律知識だけでなく、論理的思考力や表現力も評価されます。また、一般知識科目も得点しなければならず、文章理解や時事的な情報にも対策が必要です。
-
記述式問題で配点が高い
-
一般知識問題は足切り基準あり。一定点に届かないと不合格
-
判例や条文ベースの学習が必須
-
3分の1が一般知識の配点で注意
こうしたバランス型の学習計画が合格への鍵となります。
社労士試験の範囲の広さと計算問題など専門的出題の解説 – 難関ポイントの解明
社労士試験は合格率が非常に低く、特に法令科目と専門知識の幅が広い点が難しさの要因です。選択式と択一式があり、それぞれ基準点に達しないと失格となります。労災保険や年金分野では計算問題も登場し、正確な数値管理が求められます。
-
基本科目が10分野近くある
-
過去問の演習が必須だが、改正点も多いので最新知識の更新が重要
-
択一式、選択式ともに基準点割れで即不合格
-
年金・保険料計算など実務的な内容あり
幅広い知識と実務の両方をカバーするのが社労士試験対策の難しさです。
合格率と過去のデータから見る難易度の傾向 – 近年の合格者推移や特徴
両試験の合格率を比較すると、社労士のほうが難関だと言われています。下表を参考にしてください。
| 年度 | 行政書士 合格率 | 社労士 合格率 |
|---|---|---|
| 最新年 | 約11% | 約7% |
| 平均 | 10〜12% | 5〜8% |
行政書士は毎年約10%前後の合格率、社労士は多くの年で8%以下としています。どちらも難関国家資格ですが、「社労士の方がより狭き門」と言えるでしょう。
勉強時間と効率的な学習法の違い – 初心者向け推奨学習計画と教材選び
学習時間の目安は、行政書士が約600〜800時間、社労士は800〜1,000時間以上が一般的です。
-
行政書士:法令・判例重視。書籍や問題集+通信講座の併用が効果的。
-
社労士:法改正の最新情報に注意。過去問演習と模試活用、講座受講推奨。
-
短期集中型より長期戦が有効。
いずれもアウトプット重視で、記憶の定着と実務対応力を養うのが合格への近道です。
免除制度や受験資格の比較 – 行政書士受験経験者が社労士に有利なケースなど
受験資格は、行政書士は年齢や学歴不問ですが、社労士は原則として大卒や一定専門学校卒など条件あり。過去に行政書士試験合格や業務経験がある場合、一部科目免除や、勉強効率化のメリットも期待できます。
-
行政書士は誰でも受験可能
-
社労士は学歴要件有り
-
ダブルライセンス取得者は転職や独立に強い傾向
また、既に行政書士の知識がある人は法令分野の基礎力が活かせるため、社労士合格への道筋が有利になるケースも多いです。
行政書士と社労士はどっちが稼げる?年収比較・収入の現実と将来性
行政書士の平均年収・独立開業の収入モデルと安定性 – 実態に基づく実例解説
行政書士の平均年収は約300万円~500万円程度が現実的な水準とされています。特に独立開業した場合、売上やクライアント数によって幅が出やすいのが特徴です。行政書士の主な収入源は許認可申請や書類作成、相続や遺言の手続きサポートなどで、都市部では需要も多いですが、競争が激しいのも事実です。安定して高い年収を得るには、営業力やネットワーク作り、専門分野の確立がカギとなります。開業1年目は年収200万円台も珍しくありませんが、実務経験を積み、信頼を得ることで徐々に高収入が狙える職種です。
| 年収目安 | 主な仕事内容 | 特徴 |
|---|---|---|
| 300万~500万円 | 許認可/書類作成等 | 独立型が多い、収入格差大 |
| 600万円以上 | 法人案件・相続・顧問等 | 営業力・専門分野確立が重要 |
社労士の平均年収・顧問契約の安定した収入とその背景 – 報酬体系と収入増のための工夫
社会保険労務士は平均年収400万円~700万円程度で推移しています。特に中小企業との顧問契約による安定的な月額収入が特徴で、安定性の面では行政書士より優位です。就業規則作成や労働保険・社会保険の手続き、人事・労務の相談が主な業務で、信頼を積み重ねることで複数の顧問先を獲得できます。報酬アップには就業規則改定や、助成金申請サポートなどのスポット業務の拡大が効果的とされています。人事部門出身者や労務分野に強い人に向いています。
| 年収目安 | 主な仕事内容 | 特徴 |
|---|---|---|
| 400万~700万円 | 顧問契約・手続 | 顧問ビジネスで安定性が高い |
| 800万円以上 | 労務コンサル等 | 商談力・複数顧問先で伸びる |
ダブルライセンスの年収アップ効果と収入多角化のメリット – 事例や調査データの比較
行政書士と社労士のダブルライセンスを活用することで、取り扱える業務範囲が大幅に広がります。相続・許認可・労務手続きなどの複合案件をワンストップで受託できたり、法人顧客への高度なコンサルティングも可能になるため、年収1,000万円超の実例も現れています。特に中小企業やスタートアップとの継続契約を複数抱えることで、安定かつ高収入を実現しやすくなります。年収アップだけでなく、景気変動にも強い安定感やセカンドキャリアの選択肢が増える点も大きなメリットです。
| 資格構成 | 独立時の収入目安 | 差別化ポイント |
|---|---|---|
| 行政書士単体 | 300万~700万円 | 書類・許認可中心 |
| 社労士単体 | 400万~900万円 | 顧問契約・人事労務中心 |
| ダブルライセンス | 700万円~1,200万円超 | ワンストップ対応・大口案件・安定性向上 |
仕事の未来予測と需要動向 – AI・IT化による業務変化の影響と備え方
AIやIT化の進展は、行政書士・社労士業界でも単純な手続き業務の効率化が進むと見られています。しかし、法改正や人事労務に関する専門的なコンサルティング、企業ごとの個別対応など「人間力」が問われる分野は依然として強みがあります。今後はAIに代替されにくい専門知識・提案力や、ITツールを使いこなせるスキルが年収アップ・キャリア維持の鍵となるでしょう。複雑な案件や専門的な相談事に対応できる人材が、今後ますます求められていきます。
社労士・行政書士の将来性と市場競争力の差異 – 長期的な視点による考察
今後の人口減少や少子高齢化の中でも、企業の法務・労務管理や個人の資産承継ニーズは根強いものがあります。行政書士は法改正や規制緩和に影響を受けやすい一方、社労士は社会保険や人事労務のニーズと直結し、需要が安定する傾向があります。ダブルライセンスによる企業サポートや他士業連携によって、市場での競争力を持続することができます。自己成長を怠らず、業務の幅を広げていくことで、今後も高い市場価値を維持できる職業です。
資格取得の順番とキャリア設計 – 行政書士と社労士はどっちが先かの判断基準
行政書士と社会保険労務士(社労士)の資格は、どちらも法律系国家資格として幅広い分野で求められていますが、取得する順番やキャリア設計によって将来の選択肢や専門性に大きく影響します。自分の目指したい職域やキャリア像から逆算し、より適した順序の選択が重要です。たとえば「独立開業重視」や「企業就職志向」、「ダブルライセンス獲得」など目的によってベストなルートは異なります。一人ひとりに最適な道を選ぶことで、将来後悔しないキャリア設計を実現できます。
取得順序のメリット・デメリット比較 – 学習負担や免除システム含む
行政書士・社労士どっちを先に目指すべきかは、仕事の適性や受験資格、学習負担が判断基準になります。行政書士の場合、受験資格の制限がなく学歴不問で挑戦できる一方、社労士は原則「大卒以上」や独自の受験資格が必要となる点を事前に確認しましょう。また、行政書士資格を持っていることで、社労士受験時の一部科目免除が活用できる場合もあります。
| 順番 | 主なメリット | 主なデメリット |
|---|---|---|
| 行政書士→社労士 | ・学歴不問で始めやすい ・法令知識が社労士試験にも活かせる |
・社労士受験資格を満たさない場合は直接進めない |
| 社労士→行政書士 | ・労務管理の実務力を優先可 ・企業就職向き |
・大学卒業等の条件が必須 |
学習負担の面では、行政書士で基礎力を鍛えてから社労士に進む方が効率的なケースも少なくありません。
トリプルライセンス(司法書士・宅建併用含む)も含めた総合キャリアプランの提案
行政書士と社労士に加え、司法書士や宅建士との「トリプルライセンス」が注目されています。各資格の専門業務を組み合わせることで、開業・独立時の業務領域が飛躍的に広がります。例えば不動産関連なら宅建士、登記業務も扱いたい場合は司法書士、労務管理や許認可まで網羅可能です。
-
強みを活かしたワンストップ事務所運営
-
企業コンサル・行政支援業務の幅が拡大
-
地域密着型サービスで差別化が可能
「どの順番での取得が自分にとって効率的か」「ダブル・トリプルライセンスの活かし方」を考えながら戦略的な学習が求められます。
社労士や行政書士合格後のステップアップ戦略
資格取得後は開業・転職・副業など多彩な選択肢が広がります。行政書士は独立しやすく個人顧客との取引が多い傾向ですが、社労士は企業顧問契約で安定収入が見込めます。両方の資格を活かすことも可能で、近年はダブルライセンスによる付加価値が評価されています。
-
独立開業:サービスの多角化により顧客層アップ
-
法務・総務人事への転職・就職
-
大企業や士業法人でのキャリアアップ・管理職登用
-
FPや他資格との組み合わせによるシナジー効果
合格後も定期的なスキルアップや新分野の知識習得を意識し、自身の可能性を最大限に拡げることが重要です。
就職・転職・独立での実務的な選択ポイント – 行政書士と社労士はどっちが有利か
行政書士と社労士は、ともに社会や企業を支える国家資格ですが、その活かし方で現実的な選択が分かれます。就職・転職・独立の視点では、どちらが「自分のキャリア目標」に近いかを明確にすることが重要です。以下、仕事内容や活躍場面、独立した際の現実、ダブルライセンスの実利を細かく解説します。
企業内でのニーズと求人動向 – それぞれの資格保有者の活躍場面分析
行政書士と社労士の企業内ニーズには明確な違いがあります。行政書士は主に官公庁などへの書類作成や許認可申請の専門家として、総務・法務部門などでスポット的な需要が見られます。一方、社労士は給与計算・社会保険手続き・労務管理を中心に、人事労務分野で継続的な需要が根強い特徴があります。
| 項目 | 行政書士 | 社労士 |
|---|---|---|
| 企業内求人 | 少ない(法務・総務・建設業界等) | 比較的多い(人事・総務部門で活躍) |
| 活躍場面 | 許認可申請、法的文書作成 | 労務管理、社会保険手続き、相談業務 |
| 求人動向 | ピンポイント型 | 安定した需要 |
| 転職の有利さ | 大手より中小・士業事務所で有利 | 一般企業から社会保険労務士法人まで幅広い |
社労士は「人事や労務管理分野」での転職有利度が特に高く、行政書士は「専門的分野への絞り込み」で力を発揮します。
独立開業の現実と成功事例 – 開業資金、顧客獲得の工夫やリスク
独立開業を目指す場合、行政書士と社労士では「集客方法」「収入構造」「リスク耐性」に違いがあります。
| 比較項目 | 行政書士 | 社労士 |
|---|---|---|
| 開業資金 | 30万円〜60万円程度 | 30万円〜60万円程度 |
| 主要顧客 | 法人・個人・建設業・外国人 | 中小企業・顧問先 |
| 集客の工夫 | HP活用・提携士業・セミナー | 人脈・HP・企業訪問 |
| 主なリスク | 業務の季節波動、法改正による影響 | 顧問契約の継続性、競合の増加 |
| 収入の特徴 | スポット受注が中心 | 顧問契約による安定収入 |
行政書士は許認可業務に強い反面、季節変動や法改正で収入が不安定になりやすい傾向があります。社労士は顧問契約が主流のため安定収入を得やすく、独立時のリスク分散がしやすいのが特長です。
ダブルライセンス者の転職市場での強みと成功例
行政書士と社労士の両資格を取得する「ダブルライセンス」は、市場価値を大きく高めます。
-
対応可能な業務範囲が広がる
-
ワンストップサービスによる顧客満足度向上
-
大手企業や士業法人からの求人増加
-
専門性・信頼性の向上で営業面にもアピール
成功例としては、建設業や外国人雇用分野で両方の資格を活用し、行政手続きから労務管理まで一気通貫でサポートする士業事務所や、人事コンサルとして年収アップを実現した転職者も多く見られます。転職市場ではダブルライセンス者が「管理職候補」「専門職」として高く評価される傾向があります。
行政書士と社労士はどっちがオススメ?適性と目的別の選び方ガイド
資格選択の指標としての性格、業務志向、キャリアゴール別の分析
行政書士と社会保険労務士はいずれも法律系の国家資格ですが、それぞれ業務範囲や働き方、向いている性格に違いがあります。比較しやすいように下記の表にまとめました。
| 項目 | 行政書士 | 社会保険労務士 |
|---|---|---|
| 主な業務 | 官公署への書類作成・申請、許認可取得サポート | 労働社会保険手続き、給与計算、就業規則作成 |
| 顧客 | 個人、事業主、中小企業 | 企業(人事労務部門)、社長、従業員 |
| 向いている人 | 文書作成・調査が得意、独立志向 | 人と接することに抵抗がない、組織支援志向 |
| キャリアゴール | 法的な手続きのプロ、開業・独立、書類での支援 | 企業内の専門家、コンサル、人事労務部門での活躍 |
| 難易度 | 合格率約10~12%、学歴不問 | 合格率約6%、原則大卒以上が受験資格 |
行政書士は幅広い行政手続きや許認可分野が中心なので、文書作成や法律知識を活かしたい方に最適です。一方、社会保険労務士は企業や組織の“人”に関する課題解決が中心で、コミュニケーション力や調整力も重要となります。
向いている人の具体像 – 仕事内容・報酬体系からみる適性診断
どちらの資格が自分に合うかを判断する際は、求める働き方や収入イメージも大切です。
行政書士に向いている人の特徴
-
官公署や役所への申請書類作成を通じて、個人・企業の手続きを支えたい
-
独立開業に興味があり、自分のペースで働きたい
-
士業連携やダブルライセンスで業務拡大を目指したい
社会保険労務士に向いている人の特徴
-
企業の人事・労務管理、労働法の知識を生かした実務がしたい
-
顧問契約で安定した月額報酬(ストック収入)を得たい
-
職場の労使トラブルや就業規則の相談対応など“人”に寄り添う仕事がしたい
収入面では、どちらも実力次第で高収入は狙えますが、安定した収入モデルを構築しやすいのは社会保険労務士といわれています。
悩みや疑問を解消する実務ケーススタディ
実際に行政書士と社労士それぞれを選択した場合のキャリア例を紹介します。
Aさん(行政書士)
-
フリーランスとして独立。建設業や車庫証明、相続の手続きサポートに特化し年収600万円以上を実現
-
行政書士+宅建などのダブルライセンスで業務範囲を広げ、顧客の幅も拡大
Bさん(社会保険労務士)
-
企業の人事部を経て、開業社労士に転身。複数企業と顧問契約を結び月額報酬が安定
-
ダブルライセンス(行政書士+社労士)で助成金申請や人事コンサルにも活躍
このようにキャリアや業務の幅、将来性を重視して選ぶことが重要です。ご自身の性格やキャリア像と照らし合わせ、最適な資格ルートをしっかり判断しましょう。
ネガティブな口コミ・リアルな声を客観的に検証 – 行政書士と社労士にまつわる誤解と真実
「やめとけ」「悲惨」などの否定的意見の背景をデータで精査
ネット上では「行政書士は稼げない」「社労士は仕事がない」などの否定的な声を見ることが多く、資格選択に不安を感じる方も少なくありません。これらの意見の背景には、業界の現状や参入者の増加、独立開業の厳しさが密接に関わっています。
下記の表はよくあるネガティブな意見とその根拠・実際のデータをまとめたものです。
| 否定的意見 | 背景・実態 |
|---|---|
| 行政書士は稼げない | 開業直後の収入は低いが、経験次第で増加。企業顧問や許認可業務で安定収入を得ている人も多い。 |
| 社労士は仕事がない | 顧問契約の取り方や事業所との信頼構築が鍵。人手不足に悩む中小企業からの依頼増加傾向も。 |
| 資格取得は無駄 | 独立以外にも企業内資格として評価されており、キャリアの幅が広がるケースがある。 |
否定的な口コミの多くは、ごく一部のケースを強調したものや、準備不足で独立した際の失敗談がベースとなっています。どちらの資格も「期待値」と「現実」のギャップを正しく理解することが重要です。
社労士・行政書士の仕事の醍醐味・苦労を両面から解説
社労士と行政書士は、どちらも専門知識を活かして社会や企業に貢献できる資格です。細かな法律知識や実務スキルが求められますが、それだけにやりがいも大きいです。
社労士の魅力と苦労
-
労働や社会保険の専門家として相談される信頼感
-
顧問契約で安定した収入を得やすい
-
法改正への対応・クライアントフォローに膨大な時間を費やす
-
開業時は営業努力なしに顧客が獲得できない
行政書士の魅力と苦労
-
官公庁への許認可申請や、外国人ビザなど多様な業務で社会に貢献
-
独立開業しやすく幅広い分野にチャレンジできる
-
顧客獲得・案件受注までに営業・実務の両方で努力が必要
-
書類作成ミスのリスクや、AI時代の変化にも対応が不可欠
いずれも「継続的な学習」「信頼構築」「新しい分野への適応力」が成功のポイントです。
利用者の体験談から得られる教訓と希望のストーリー
実際に行政書士や社労士として活躍する方々の体験談には、資格選択で迷っている方へ役立つリアルな教訓と希望が含まれています。
主な体験談で見られる傾向
-
最初は収入が不安定でも、地道な営業と信頼構築で2~3年目から安定化
-
ダブルライセンスを取得し、事務所の業務範囲が広がり売上も倍増したケース
-
一度会社を辞めた後も、セカンドキャリアとして資格が強みになった
-
自分に合った分野(相続、企業労務、入管業務など)を選ぶことで充実感や成長実感につながった
得られる教訓
- 資格取得はゴールでなくスタート。実務・人脈・学習が成否を分ける
- ネガティブな噂以上に、努力次第でチャンスが広がる実感
- 失敗や苦労を経てこそ、専門家としてクライアントに信頼されるようになる
行政書士や社労士のリアルな声を知ることで、表面的な噂や誤解だけに惑わされず、自分に合った道や将来像をイメージしやすくなるはずです。
行政書士と社労士はどっちを目指す人へ 実践的よくある質問と回答集
難易度・年収・就職・独立に関する質問のピックアップと詳細解説
行政書士と社労士、どっちが難しい?どっちが稼げる?キャリアや仕事は?これらは多くの方が資格取得を検討する際に直面する疑問です。
難易度面では
-
社労士は受験資格として原則大学卒が必要ですが、行政書士は誰でもチャレンジできる点が特徴です。
-
試験合格率はおおむね行政書士は10~15%、社労士は6~8%程度と、僅差ながら社労士の方がやや難易度が高いです。
年収・就職面では
-
行政書士の平均年収は約400万~600万円、社労士は450万~700万円といわれており、稼げる傾向は社労士がやや優勢です。
-
就職・転職市場では、社労士は人事労務の専門家として企業内外で重宝されています。行政書士は独立開業で自分の色を出しやすい反面、営業力も重要です。
独立開業を検討している場合
- 行政書士は比較的独立しやすい資格とされます。社労士は安定した顧問契約で基盤を築けるのが魅力です。
受験資格・免除制度・ダブルライセンス関連の疑問解消
受験資格や免除制度の違い、ダブルライセンス取得時のメリットについて整理します。
-
行政書士の受験資格
- 年齢・学歴・職歴不問で、誰でも受験可能です。
-
社労士の受験資格
- 原則大学卒以上(短大・高専等含む)、または一定の実務経験が必要です。
免除制度
-
行政書士では特認制度や一部公務員経験による科目免除がありましたが、現在は廃止されています。
-
社労士試験にも免除制度があり、科目一部免除や、他の国家資格や大学での履修状況により要件が変わります。
ダブルライセンスの効果
-
行政書士×社労士のダブルライセンスは、会社設立から労務顧問手続きまで幅広いサービス展開ができ、独立や転職で希少性が高まります。
-
特に中小企業支援やコンサルティング分野での評価が高く、求人市場でも有利になるケースが増えています。
学習法・試験日・更新制度に対する具体的な回答例
学習法のポイント
-
行政書士は法律初学者にも対応したテキスト・講座が豊富です。試験範囲が広いため早めの学習開始がカギです。
-
社労士は労働法・社会保険の実践知識が問われます。過去問演習と法改正のキャッチアップが重要です。
試験日・受験スケジュール
-
行政書士:例年11月に実施、申込は8~9月。
-
社労士:例年8月に実施、申込は4~5月。
更新制度について
-
行政書士は登録後に継続的な研修が推奨されていますが、義務付けはありません。
-
社労士も法的な更新義務はありませんが、実務能力向上のため講習参加が推奨されています。
比較表 – 業務内容・難易度・平均年収・独占業務の一覧
| 資格 | 主な業務内容 | 難易度(合格率) | 平均年収 | 独占業務 |
|---|---|---|---|---|
| 行政書士 | 各種許認可手続書類作成・申請 | 約10~15% | 400~600万円 | 官公署等への許認可申請書類の作成・提出代行 |
| 社会保険労務士 | 労働社会保険の手続・労務コンサル | 約6~8% | 450~700万円 | 労働・社会保険手続代行、就業規則の作成 |
| ダブルライセンス | 企業支援の包括コンサルティング | – | 600~900万円以上 | 両方の独占業務をカバーし多様なサービス提供 |
行政書士と社労士、それぞれの強みや特徴を把握し、自分の適性・将来像に合った選択をおすすめします。