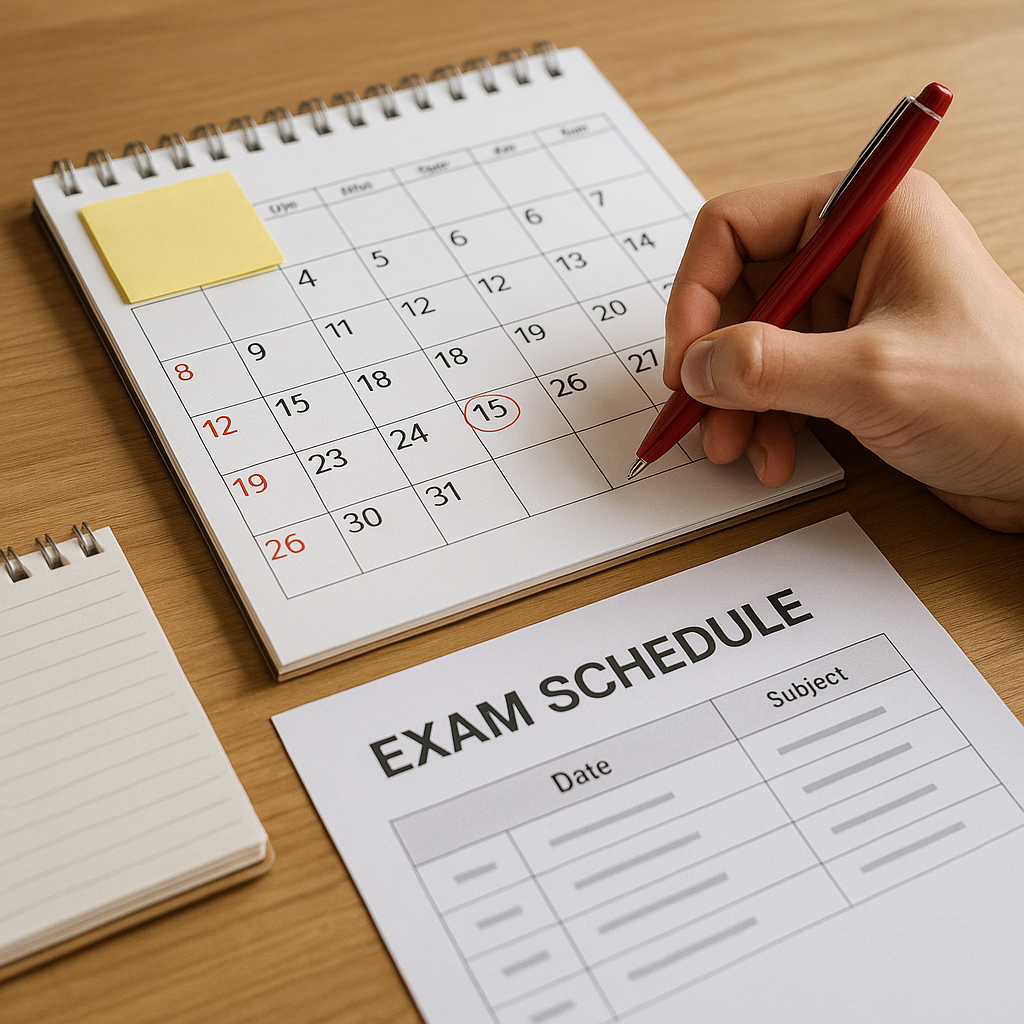「いよいよ公認会計士試験【2025年版】が目前に迫り、試験日程や出願スケジュールの最新情報はもうしっかり把握できていますか?毎年、短答式は12月と5月、論文式は8月開催が通例で、【2025年は短答式第Ⅰ回が5月25日、第Ⅱ回が12月7日、論文式は8月15日~17日の3日間】と発表されています。
出願期間や試験当日のタイムテーブルは年度ごとに微妙に異なり、近年ではオンライン出願のトラブルや試験会場の急な変更も少なくありません。強調したいのは、「最新の公式発表を見落とすと、出願受付に間に合わない」「予定変更を知らずに受験機会を逃す」という実際の事例も多数存在する点です。
「日程管理が苦手で情報を整理できない」「毎年どこかで公式発表を見逃しがち…」と悩んでいる方も多いはず。本記事では、年度ごとの公認会計士試験日程を一覧で比較し、短答式・論文式の違いや出願から合格発表までの流れを、重要ポイントを抜け漏れなく分かりやすくまとめました。
最後まで読むことで、「出願のうっかりミスや見落とし」を防ぎ、計画的な勉強と手続きで万全の本試験当日を迎えられるはずです。今こそ、あなたの一歩を後押しする正確な情報を手に入れてください。
公認会計士試験は日程と年間スケジュールの全体像を徹底解説
公認会計士試験は、経済・財務・監査分野で活躍するプロを目指す方にとって欠かせない重要なステップです。試験は年間を通じて複数回実施されるため、出願から合格発表までの流れや日程を正しく理解することが合格への第一歩となります。ここでは、令和7年(2025年)・令和8年(2026年)を中心に、過去・今後の公認会計士試験の日程やスケジュールをわかりやすく解説します。特に、日程の比較、試験ごとの特徴、出願・合格発表までの流れなど、受験生が知っておくべき最新のポイントを整理しています。
年度ごとの公認会計士試験は日程比較
公認会計士試験は、年度ごとに日程や出題スケジュールが異なります。主要な年度の日程を整理した比較表で、直近の試験スケジュールがひと目でわかります。
| 年度 | 短答式試験(第Ⅰ回) | 短答式試験(第Ⅱ回) | 論文式試験 | 合格発表 |
|---|---|---|---|---|
| 令和6年 | 2024年12月8日 | 2025年5月25日 | 2025年8月22~24日 | 短答:2025年1月・6月論文:2025年11月 |
| 令和7年 | 2025年12月7日(予) | 2026年5月下旬(予) | 2026年8月下旬(予) | 短答:2026年1月・6月論文:2026年11月 |
| 令和8年 | 2026年12月(予) | 2027年5月(予) | 2027年8月(予) | 短答:2027年1月・6月論文:2027年11月 |
このように、短答式試験は毎年2回、論文式試験は1回実施され、それぞれの合格発表も年2~3回設定されています。近年はインターネット出願や公式サイトでの情報発信も充実しており、日程の把握が容易になっています。
短答式試験と論文式試験の日程の違いと特徴
公認会計士試験は、短答式試験と論文式試験に大別され、それぞれに日程や特徴の違いがあります。
- 短答式試験 ・例年、年2回(5月・12月が基本)実施
・出願期間は試験約3か月前に設定
・午前中中心に実施され、複数科目を短時間で解答 - 論文式試験 ・年1回、8月下旬に3日間連続で実施
・出願は第Ⅱ回短答式試験の合格後
・企業法・監査論・財務会計など、幅広い分野で記述式解答が求められる
特徴
短答式試験は合否が比較的早く判明し、基礎力を測る内容。論文式試験は総合的な知識・思考力が問われるため難易度が上がり、科目ごとの時間割に沿って複数日かけて実施されます。2025・2026年もこの構成は維持される予定です。
年間フローチャート:出願から合格発表までの流れ
公認会計士試験の年間スケジュールは、出願から合格発表まで一連の流れがあります。効率よく受験するためには、各ステップを事前にチェックしておくことが重要です。
- インターネット出願手続き
公式マイページにログインし、必要情報を登録・提出 - 受験票発行・試験会場確認
実施1か月前に受験票や会場情報が公開 - 短答式試験受験/合格発表
年2回の試験結果を確認 - 論文式試験出願・受験
試験実施後、論文式の出願が可能 - 論文式試験の合格発表
合格後、会計士登録や実務補習へ進む
最新の予定や会場案内、試験時間割も随時更新されているため、公式発表をこまめにチェックすることが成功へのカギとなります。受験生はスケジュールを可視化し、余裕を持って各手続きを進めるよう心掛けましょう。
出願期間・申し込み方法・オンライン手続きの詳細と注意点
出願期間の具体的スケジュールと期限管理ポイント
公認会計士試験の出願期間は例年、短答式・論文式それぞれに設けられています。令和7年(2025年)の主なスケジュールは下記の通りです。
| 試験区分 | 出願期間 | 試験日 |
|---|---|---|
| 第Ⅰ回短答式 | 2024年8月23日~9月12日 | 2024年12月8日 |
| 第Ⅱ回短答式 | 2025年2月3日~2月25日 | 2025年5月25日 |
| 論文式試験 | 第Ⅱ回短答式合格後受付 | 2025年8月22日~24日 |
期限管理のポイント
- 出願期間を過ぎると一切受け付けられません。
- 出願日はシステム混雑が予想される締切間際を避けて手続きを行うのがおすすめです。
- 期日や受付開始日は試験年度によって前後する可能性があるため、公式サイトで常に最新情報を確認してください。
インターネット出願の操作手順と注意点
公認会計士試験の申し込みはインターネット出願が必須です。正確かつスムーズに出願を完了するため、次の点に注意してください。
- 公式ウェブサイトからマイページ作成
- 個人情報や出願内容を正確に入力
- 必要書類(写真データなど)のアップロード
- 受験料の支払い手順に沿って決済
- 全ての入力・添付書類を再度確認し出願完了
注意点
- 不備や未入力がある場合、出願が無効となることがあります。
- 顔写真などの画像データは指定サイズ・形式を守る必要があります。
- 受験料の入金忘れや決済不備も認められません。
- 提出完了後は必ず控え(受付番号や確認画面)を保存してください。
試験会場の選び方と直近の変更情報
試験会場は、全国の主要都市に設置されています。出願時、希望会場を選択できるケースがほとんどですが、定員オーバーの場合は他会場になる場合もあります。
会場選びのポイント
- 交通アクセスや当日の移動時間を考慮して選ぶ
- 会場の所在地・詳細は、試験日およそ1か月前に公式発表される
- 直前に会場が変更される場合もあるので、こまめな確認が重要
主要都市別の会場例(最新情報は年度ごとに要確認)
| 都市 | 主な会場例 |
|---|---|
| 東京 | 大学・研修施設等 |
| 大阪 | 大学・試験センター |
| 名古屋 | 大学・会議場 |
| 札幌・福岡 | 大学・市内施設 |
注意点
- 体調や天候、交通事情も考え、余裕をもった移動計画を立てましょう。
- 出願後に住所変更や会場詳細公開後に疑問点がある場合は、必ず早めに試験事務局へ問い合わせしてください。
短答式試験の日程と時間割、試験科目の構成詳細
第Ⅰ回・第Ⅱ回短答式試験の日程と時間割一覧
公認会計士試験の短答式は、年2回実施されます。2025年の日程は以下の通りです。毎回、午前から午後にかけて複数科目を受験しますので、時間割の把握が重要です。
| 試験回 | 試験日 | 出願期間 | 合格発表日 |
|---|---|---|---|
| 第Ⅰ回 | 2024年12月8日 | 2024年8月23日~9月12日 | 2025年1月17日 |
| 第Ⅱ回 | 2025年5月25日 | 2025年2月3日~2月25日 | 2025年6月20日 |
短答式試験の標準的な時間割は以下のようになっています。
| 科目 | 試験開始 | 試験終了 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 財務会計論 | 9:00 | 10:30 | 90分 |
| 管理会計論 | 11:10 | 12:10 | 60分 |
| 監査論 | 13:10 | 14:10 | 60分 |
| 企業法 | 14:50 | 15:50 | 60分 |
受験日程や会場、時間割は変更となる場合がありますので、最新情報は必ず公式発表で確認してください。
短答式試験の科目ごとの出題形式と配点の解説
短答式試験は4科目で構成され、それぞれに明確な出題形式と配点基準が設けられています。重要なポイントは以下の通りです。
- 財務会計論(得点比率:40%) ・主に会計基準・会計理論・計算問題が中心。
・マークシート方式で、配点が最も高い科目です。 - 管理会計論(得点比率:20%) ・原価計算や管理会計の理論・実務を問う設問が多い。
・計算問題と理論問題のバランスが特徴です。 - 監査論(得点比率:20%) ・監査の基本概念や基準、手続きについて幅広く問われます。
・理論主体で、最新の基準改定にも対応しています。 - 企業法(得点比率:20%) ・会社法および関連法規が中心。
・条文理解と適用能力が求められます。
配点のバランスを踏まえ、優先すべき科目や学習順序を明確にして計画的に対策を進めてください。
試験当日の持ち物・注意点
当日は忘れ物やトラブルを防ぐため、必要な持ち物と注意事項を事前にチェックすることが重要です。
- 受験票・本人確認書類
- HBまたはBの鉛筆・消しゴム
- 時計(通信・計算機能なしのもの)
- 昼食・飲料水(会場による制限に注意)
注意点一覧
- 会場の案内や座席番号は試験前に必ず確認してください。
- スマートフォンや電子機器は必ず電源を切り、カバンにしまってください。
- 試験中の不正行為や遅刻は、失格対象となります。
- 万が一の体調不良への備えとして、必須薬やマスクなども持参を推奨します。
充実した準備で当日は落ち着いて実力を発揮できるよう、しっかり対策を行いましょう。
論文式試験の日程と試験時間割、科目選択のポイント
論文式試験の開催日程と3日間の時間割詳細
公認会計士試験の論文式試験は毎年8月下旬の3日間にわたり実施されます。受験には各日の時間割を正確に把握し、スケジュール管理を徹底することが重要です。以下は2025年の論文式試験に基づく時間割の例です。
| 日程 | 午前(9:00〜12:00) | 午後(13:30〜16:30) |
|---|---|---|
| 1日目 | 企業法 | 管理会計論 |
| 2日目 | 監査論 | 租税法/選択科目 |
| 3日目 | 財務会計論(計算・理論) | 経営学/民法/統計学 |
会場は毎年公式サイトで公表され、東京、大阪など全国主要都市が設定されています。試験の各科目は午前・午後で分かれて行われ、学習した内容の実践力が問われます。
必須科目・選択科目の概要と対策ポイント
論文式試験の科目は必須科目と選択科目に分かれています。必須科目は企業法、管理会計論、監査論、財務会計論(計算・理論)、租税法の5つです。選択科目は経営学、民法、統計学から1科目を選択する形式になっています。
- 必須科目
- 企業法
- 管理会計論
- 監査論
- 財務会計論(計算・理論)
- 租税法
- 選択科目(1科目選択)
- 経営学
- 民法
- 統計学
対策のポイントは、過去の出題傾向を分析するとともに、論理的思考と記述力の強化です。選択科目は自身の得意分野や学習状況を考慮し、無理なく高得点が狙える科目を選ぶとよいでしょう。各科目とも最新の出題範囲や公式情報の確認が必要です。
論文式試験の合格基準と評価方法
論文式試験の合格基準は全科目の総合点で60%以上かつ、各科目で基準点(40%程度)を下回らないことが求められます。すべての必須科目と選択科目の総合評価により合否が決まります。
- 総合得点率60%以上
- 各科目ごとの基準点(原則40%)を下回らないこと
評価方法は、各科目の論述解答をもとに知識だけでなく論理的な思考力、解釈力、記述力まで幅広く審査されます。得点率配分や部分点獲得も重要なため、最後まであきらめず丁寧に解答することがポイントです。
合格発表は例年11月下旬に公式サイトで行われ、合格者には今後の実務経験や登録手続きに関する案内が届きます。各年の実施状況や合格点は変動するため、最新情報の確認が不可欠です。
合格発表の日程・合格率の推移と合格後の手続き
合格発表の具体的な日時・確認方法と注意点
公認会計士試験の合格発表日は、各年度や試験区分によって異なります。たとえば2025年(令和7年)度の場合、第Ⅰ回短答式試験は2025年1月17日、第Ⅱ回短答式試験は6月20日、論文式試験は11月21日にそれぞれ発表される予定です。合格発表は主に下記の方法で確認できます。
- 公式ウェブサイト上の掲載
- ウェブでの合格者番号一覧検索
- 合格者への合格通知書郵送
合格者は番号のみが発表されるため、不合格の場合も自身で番号を必ず確認してください。時間帯やアクセス集中によるサイト混雑も予想されるため、複数回の確認をおすすめします。発表日時直後は特にアクセス増加が見込まれますので事前に準備しておくと安心です。
過去数年の合格率推移と試験難易度の変動分析
過去数年の合格率は、試験ごとに変動しています。特に短答式と論文式で差が大きい傾向がみられます。直近の推移は以下の通りです。
| 年度 | 短答式合格率 | 論文式合格率 |
|---|---|---|
| 2022年 | 10.8% | 11.6% |
| 2023年 | 11.5% | 11.2% |
| 2024年 | 12.0% | 12.3% |
短答式試験では10〜12%、論文式でもおよそ11〜12%前後となっており、いずれも非常に厳しい水準です。年度による科目の難易度バランスや出題傾向の変化もあるため、直前年度の傾向把握と対策が不可欠です。また、令和7年・令和8年に向けては分析に基づいた準備が重要となります。
合格後の登録から公認会計士になるまでの流れ解説
合格発表後は公認会計士登録手続きに進みます。登録までの主な流れを以下に示します。
- 必要書類の提出と手続き(身分証明・写真・合格証)
- 公認会計士協会での書類審査
- 登録料納付
- 公認会計士名簿への登録
登録が完了すると、公認会計士として正式な活動が可能となります。加えて、合格後に実務補習や研修受講が求められます。実務経験や研修修了は多くの企業などで重視されるため、早めに準備を進めることが合格後のキャリアアップに繋がります。
これらのステップを計画的に進めることで、公認会計士としての活動をスムーズにスタートできます。
試験対策のための日程を踏まえた効果的な勉強スケジュールと模試日程
試験日程に基づく短答式・論文式別勉強スケジュール例
公認会計士試験は短答式と論文式に分かれており、それぞれに最適な学習スケジュールが必要です。短答式試験は年2回、12月と翌年5月に実施されるため、12月受験を目指す場合は7月から本格的に学習開始し、直前2か月は過去問と模試中心の演習が重要となります。5月受験を目指す場合でも、12月には基礎力を仕上げておくと良いでしょう。論文式試験(8月)は短答式合格後から逆算し、答練や模試、実践的な演習を多く取り入れることが効果的です。学習スケジュール例としては、毎週のタスクとともに、重要テーマへの重点配置や苦手科目の克服時間を明示的に確保するのがおすすめです。
主要予備校の模試・答練開催日程一覧と特徴比較
公認会計士試験対策で多くの受験生が活用する予備校の模試・答練には、それぞれ特徴があります。以下のテーブルで代表的な大手予備校の開催日程・特徴を比較します。
| 予備校 | 短答式模試日程 | 論文式模試日程 | 特徴 |
|---|---|---|---|
| TAC | 11月・4月 | 7月 | 全国規模・詳細な個別成績表・解説講義付き |
| 大原 | 10月・3月 | 6月 | 分析が細かい・全科目対応・反復演習プログラム |
| 資格の学校LEC | 10月・4月 | 6月 | 会場・自宅受験対応、効率学習ツールが豊富 |
予備校模試は本試験と同様の時間割で実施され、弱点把握や合格基準の確認に適しています。受験生は日程に合わせて計画的に参加することで実力を客観的に測ることができます。
効率的な学習法・合格者の体験談引用
効率的な合格への近道は、インプットとアウトプットをバランス良く取り入れることです。短答式試験対策では、重要論点を繰り返し学習し、定期的な過去問演習で実戦力を養うことが不可欠です。一方、論文式試験では答案練習と添削指導が大きな効果を発揮します。
合格者の多くは「出題傾向を過去問から分析し、苦手分野は予備校講師のアドバイスを活用した」「答練や模試後には必ず復習し、成績表をもとに弱点克服に集中した」と体験を語っています。また、生活リズムを一定に保ち、学習習慣を固定化することも成功のカギです。
適切なスケジュール管理と定期的な模試活用、そして合格者の実践例から自分に合う学習スタイルを見つけることが合格への最短ルートです。
試験制度の概要と制度変更・最新公示の反映
公認会計士試験の制度概要と実施主体
公認会計士試験は、財務会計・監査分野の専門家を育成するために設計された国家試験です。実施主体は金融庁の監督下にある公認会計士・監査審査会で、試験の信頼性と公正性が確保されています。
試験は主に短答式試験と論文式試験の2段階に分かれており、短答式は年2回、論文式は年1回行われています。試験会場は東京や大阪など主要都市に設けられています。受験申込はインターネット出願方式が採用され、各受験者は専用のマイページから登録や申込手続きを行う必要があります。
試験科目は財務会計論・管理会計論・監査論・企業法・租税法・経営学など多岐にわたり、幅広い専門知識が求められます。全科目の合格により、公認会計士資格への道が開かれます。
近年の制度変更と今後の見通し
近年、公認会計士試験の制度にはいくつかの変更が加えられています。出題分野や科目ごとの出題比率の調整、および受験方法の多様化が特徴的です。特にインターネット出願の導入は受験者にとって大きな利便性向上につながりました。
また、直近の動きとして、令和7年・令和8年の短答式および論文式試験の日程が公示されています。試験日や出願期間は年度ごとに発表されるため、常に最新の公式情報を確認することが大切です。受験科目の一部免除制度や実務対応を重視した出題傾向も引き続き進んでいます。
今後はデジタル社会への対応や、実務に密接に結び付いた問題の出題がより一層進む見込みです。
出題範囲の最新情報と対応のポイント
出題範囲は時流に合わせて毎年見直しが実施されています。2025年度以降は、財務会計論および監査論においてデジタル会計やサステナビリティ関連のトピックが拡充されています。経営学や企業法でも現代企業の動向に強く即した内容が加わっています。
最新の出題範囲は公式ウェブサイト上で公開されており、各科目の具体的な論点や配点比率についても定期的に更新されています。効率的な対策のためには以下の点を意識すると効果的です。
- 最新の公式出題範囲を必ず確認する
- 合格に直結する重要科目・分野を優先的に学習する
- 過去問やテキストで頻出論点を繰り返し練習する
- 時事的な会計情報や企業動向にもアンテナを張る
公式の日程や制度・範囲変更情報は定期的に確認し、万全な試験対策を進めることが合格への近道となります。
受験生の疑問に応える日程関連Q&Aと注意事項まとめ
日程に関するよくある質問(試験開催頻度・申込締切など)
公認会計士試験に関する日程のよくある質問と回答は次の通りです。
| 質問 | 回答 |
|---|---|
| 年に何回試験がありますか? | 短答式は年2回(12月と5月頃)、論文式は年1回(8月頃)実施されます。 |
| 最近の日程は? | 2025年は短答式が5月25日と12月8日、論文式が8月22~24日予定です。 |
| 出願期間は? | 各回で出願締切日が異なるため、公式サイトで最新情報を必ず確認しましょう。 |
| 出願方法は? | オンライン出願が基本です。マイページから申込・確認ができます。 |
申込締切日は変更される場合があるため、余裕をもって準備することが大切です。
出願・受験に関するトラブル事例と回避策
公認会計士試験の出願や受験では、以下のようなトラブルが発生しやすいです。
- 出願期限の見落としや入力ミス 申込内容や期限をよく確認し、不備がないか送信前にチェックしましょう。
- 会場の確認漏れ 試験会場は都道府県・都市ごとに指定されます。1か月前前後に発表されるため、メールや公式ページを必ず確認しましょう。
- 必要書類の未提出 証明写真や必要添付書類は不備があると無効になることがあります。事前にリストを作成し、準備の漏れがないかを確認すると安心です。
- インターネット環境トラブル 出願手続きはパソコンやスマートフォンで行います。ネットの混雑が予想される締切直前は避けて、余裕をもって申請しましょう。
万が一トラブルが発生した場合は、速やかに運営窓口へ問い合わせて早期解決を図ることが重要です。
合格率や難易度に関する実態解説
公認会計士試験は難関資格として知られており、合格への道のりは決して簡単ではありません。
- 合格率の目安 短答式試験の合格率は約10~15%、論文式試験は約10%前後で推移しています。年度により若干上下があります。
- 要求される学習量・時間 合格までには平均で2,000~3,000時間程度の学習が必要とされ、計画的な対策が不可欠です。
- 独学合格者は少数派 専門学校の講座や予備校を利用する受験生が多く、教材選びや情報収集も重要なポイントです。
| 項目 | 短答式 | 論文式 |
|---|---|---|
| 合格率 | 10~15% | 約10% |
| 年間実施回数 | 2回 | 1回 |
| 試験範囲 | 会計学・監査論ほか | 企業法・租税法ほか |
継続的な学習と正確な情報収集が合格への近道となります。
公認会計士試験関連の最新ニュースと公式発表速報解説
最新の公的発表の要点まとめ
2025年の公認会計士試験について、公式発表に基づいた情報が公開されています。試験の区分ごとに日程や出願方法の最新情報が明示され、受験生が間違いなく手続きを済ませるための詳細案内がされています。とくにインターネット出願の導入拡大や、出願手続きの厳格化が注目されています。
| 試験区分 | 実施日程 | 出願期間 | 主な変更点 |
|---|---|---|---|
| 短答式第Ⅰ回 | 2024年12月8日 | 2024年8月23日~9月12日 | オンライン出願必須 |
| 短答式第Ⅱ回 | 2025年5月25日 | 2025年2月3日~2月25日 | 出願期間短縮 |
| 論文式 | 2025年8月22日~24日 | 試験直後案内予定 | 受験会場一部見直し |
このように、各試験の基本情報が分かりやすく整理されています。今後も公式発表の更新に注意が必要です。
直近の試験日程変更と今後の影響
最近の公認会計士試験では、日程や会場に関する変更が複数発表されています。理由としては、受験者数増加や試験運営の効率化などが挙げられます。この影響で、会場の分散化や、地方都市での試験開催回数が調整されています。
特に、以下の点に注意してください。
- 試験会場が毎年一部変更されるため、開催都市やアクセスの確認が必要です。
- 出願期間は従来よりも短縮されている場合があり、手続き忘れ防止のための早めの準備が求められます。
- 時間割の一部に調整が入り、論文式試験では科目ごとの開始・終了時刻に変更があります。
今後は、感染症対策や自然災害時の対応としてオンライン発表や急な変更の可能性もあります。正確な情報の入手と各自の受験計画の柔軟な見直しが重要です。
受験生が注意すべき最新トピック
最新の試験情報に伴い、受験生は複数の大切なポイントを押さえることが必要です。
- 公式ウェブサイトでの最新発表の定期確認 試験日程・時間割・会場は直前で変更の可能性があるため、必ず公式発表を確認しましょう。
- マイページでの出願状況の管理 出願手続きはすべてオンライン管理となり、期限を過ぎると一切受付不可となります。
- 会場案内や持ち物チェックの徹底 試験前に受験番号や会場案内、持参物を確認し、当日は余裕を持って移動しましょう。
- 過去の合格発表状況や体験談の活用 同年度の合格発表日と流れを事前に押さえ、次の学習アクションにつなげやすくしましょう。
不明点がある場合は、迷わず公式問い合わせ窓口や公認会計士協会に相談し、最新の正確な情報を得ることが大切です。情報収集と慎重な行動で、安心して本番を迎えましょう。